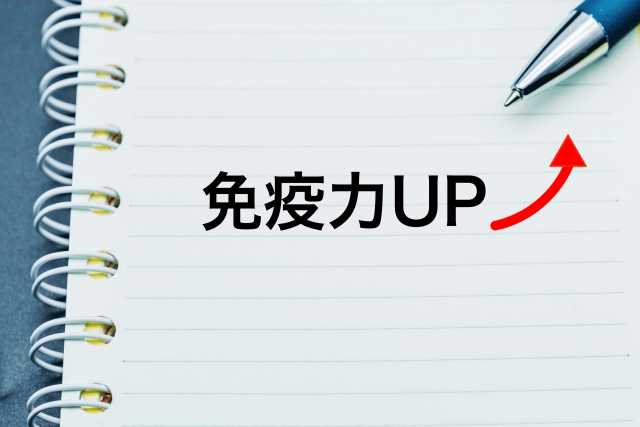いろいろあるヨーグルト。一番のおすすめってなに?
2022年最後のコラム、主役はヨーグルト!
今年もあと少しとなりました。
2022年、日本栄養検定協会のコラムを読んでいただき誠にありがとうございました。
さて、2022年最後にお届けするのは、ヨーグルトの選び方についてです。
スーパーのヨーグルトコーナーに行くと、たくさんの種類のヨーグルトが売っています。
どれを選べばいいのか分からない。。。ということはありませんか。
最近は、さまざまな機能性をうたったものも多いですよね。
そこで、どのように選んだらよいかを簡単に解説してみたいと思います。

ヨーグルトを食べるのは、腸内環境を良くしたい、とか、腸内環境を良くすることで体の調子を整えたい、などの理由で食べる方が多いと思います。
ヒトの腸内環境(腸内細菌叢)は、ひとりひとり違います。
どのような細菌が腸内に住み着いているのかは、その人の母親から受け継いだものや、生まれ育った地域、何を食べてきたのか、ストレスの状況など、さまざまな要因によって左右されます。

でも、必ずだれでも腸内に持っている菌があります。
それは、ビフィズス菌です。特に乳児の頃が一番多く、加齢と共に減っていきます。
ビフィズス菌以外の腸内細菌は、その人の腸内環境によって持っているものと持っていないものがあると考えられます。そのため、ヨーグルトを食べても体に合うなと感じるものと、ちょっとよく分からないなあ、と感じるものがあるはずです。
せっかく食べるのなら、できるだけ、体に合う!と感じるものを食べたいですよね。
ということで、どのヨーグルトを選んでよいのか分からない場合、ひとまず誰でも必ず腸内に持っているビフィズス菌入りのヨーグルトがおすすめです。

ビフィズス菌にも種類があり、各メーカーから様々なものが販売されていますので、これを1~2週間ほど食べてみて、特に体に合うな、と感じたものを選んでみてはいかがでしょうか。
ビフィズス菌以外の乳酸菌が入ったヨーグルトも、同じようにしばらく食べてみて、体に合うと感じたものを選ぶのがおすすめです。
自分の体には、どの菌が合うのかな?と考えながら、いろいろ試してみるのも楽しいかもしれません。
ヨーグルトに含まれる菌のほとんどは、それぞれのメーカーの研究によって獲得したオリジナルの菌です。
研究と努力の積み重ねの結果である様々な菌をありがたくいただきつつ、2023年も元気にすごしたいですね。
=============================
栄養学の基礎がしっかりと学べて、家庭や職場で役立つ正しい知識が身につく「栄養検定【通信・WEB講座】」の受講もオススメです。

日本栄養検定協会では
毎週月曜日、午前8時に栄養や食についての情報を発信中です♪
ご登録いただけましたら、毎週じっくりとお楽しみいただけます^^
こちらからご登録くださいね!
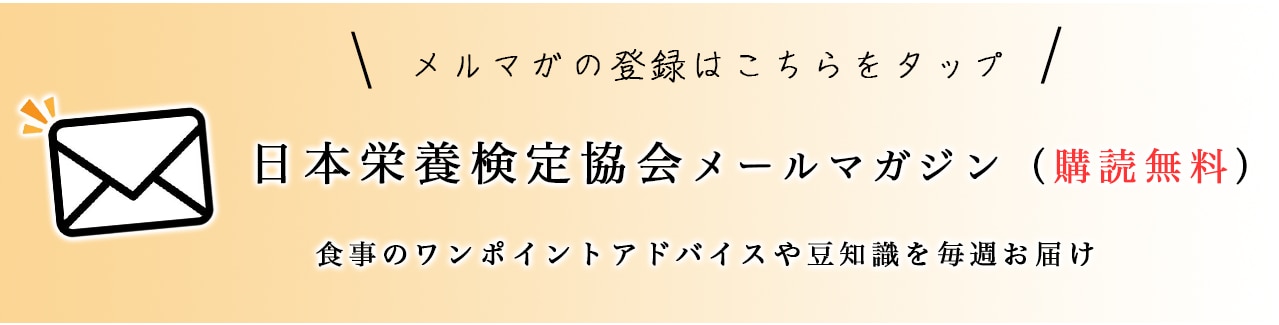
栄養に関する情報や、協会からのご連絡が届く公式LINEの登録は
こちら
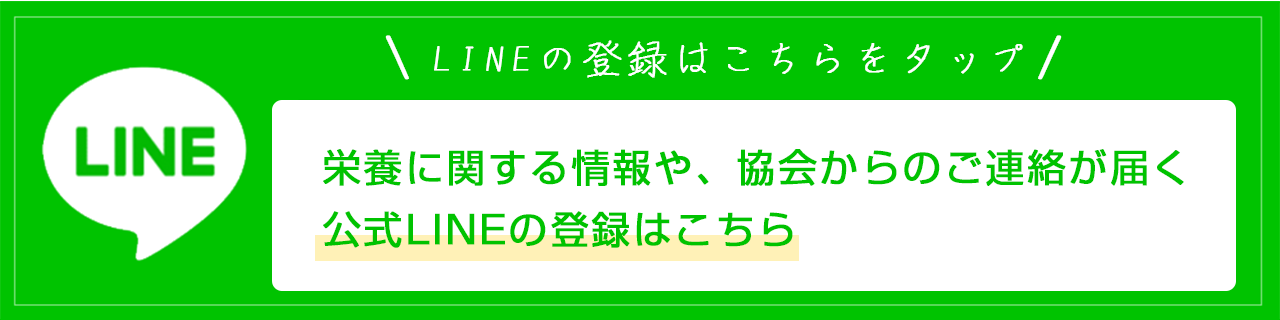
=============================