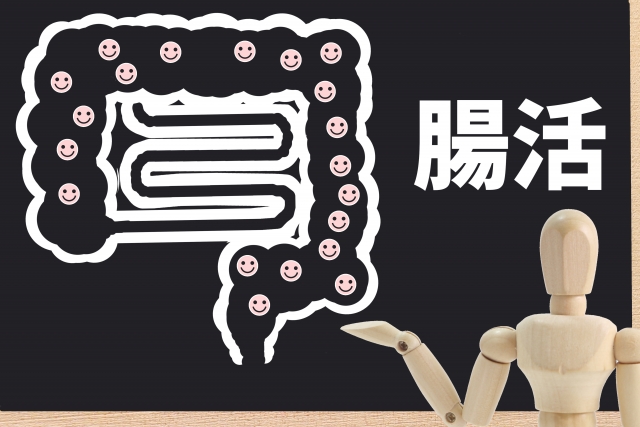キムチの機能性とは?
免疫力アップに、腸活に!キムチがあなたの体を変える
本日は、発酵食品であるキムチの機能性について見てみたいと思います。

スーパーの漬物売り場に行くといろんなキムチが売っていますよね。
実は、キムチとして売られているものであっても、作り方がまったく違うものが同じキムチとして売られています。
ひとつは、乳酸発酵で作られた伝統的なキムチと、もうひとつは、乳酸発酵していないキムチ味をつけた浅漬けの一種です。
日本では食品表示などの基準にキムチは発酵していなければならないという決まりがないため、発酵していない浅漬けタイプもキムチとして売られています。

今回は、乳酸発酵で作られたキムチについて見てみたいと思います。
キムチに含まれる乳酸菌は、食材や作り方、保存方法によって違ってきますが、Lactobacillus(ラクトバチルス)、Leuconostoc(ロイコノストック)、Weissella(ワイセラ)属は、キムチに含まれている一般的な乳酸菌です。
こうした乳酸菌は、「適切な量を摂取したときに宿主の健康に有益な作用をもたらす生きた微生物」、つまりプロバイオティクスとされています。
特に人の体に有益な働きがある機能性という点で考えるとラクトバチルス属とワイセラ属に着目したいと思います。
ラクトバチルス属には、抗菌活性や抗酸化能を持つ菌株も多く、免疫機能調整・整腸効果が期待されています。
ワイセラ属には、食中毒菌に対する抗菌活性などがあるとされています
そのほかにも、
• 腸内細菌叢の改善
• 炎症の抑制
• コレステロール低下
• 肥満予防
• 抗酸化・免疫強化
など、キムチには、さまざまな機能性が報告されています。
キムチの乳酸菌、特にラクトバチルスは酸に強いため、
生きたまま腸に届く可能性が高いという特徴があります。
ただし、加熱すると多くが死菌となってしまうため、
キムチの機能性を期待するのであれば、加熱せずに
そのまま食べるのがおすすめということになります。

ご飯のお供や納豆と混ぜる、野菜や海藻などと和え物にする、
卵と混ぜる、など手軽に美味しく食べることができますね。
辛いので万人向きとは言いづらいキムチですが、
是非、食事に取り入れて行きたいですね!
=============================
栄養学の基礎がしっかりと学べて、家庭や職場で役立つ正しい知識が身につく「栄養検定【通信・WEB講座】」の受講もオススメです。

日本栄養検定協会では
毎週月曜日、午前8時に栄養や食についての情報を発信中です♪
ご登録いただけましたら、毎週じっくりとお楽しみいただけます^^
こちらからご登録くださいね!
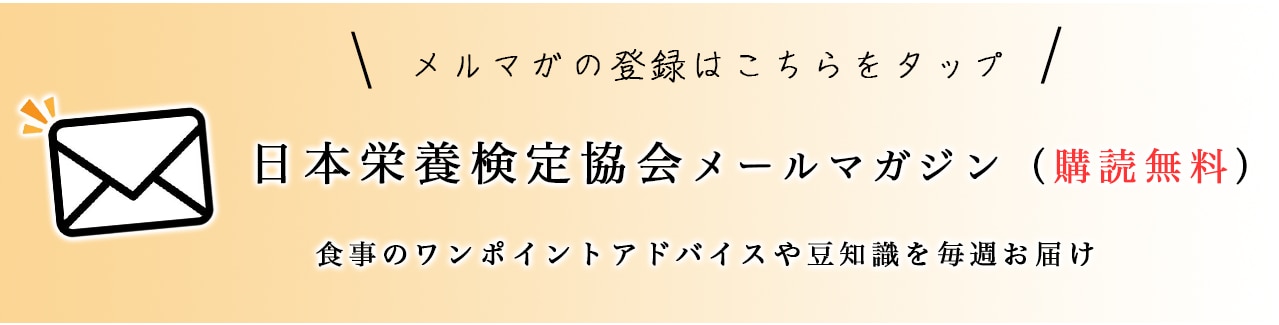
栄養に関する情報や、協会からのご連絡が届く公式LINEの登録は
こちら
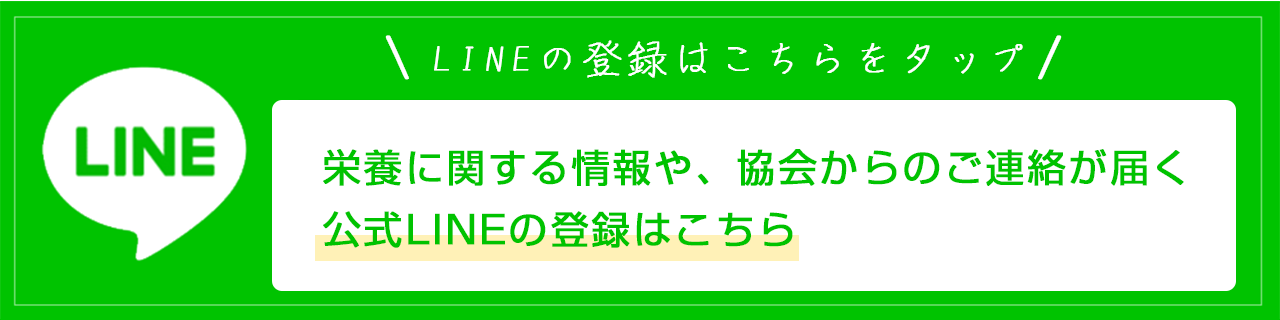
=============================